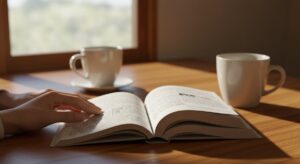あらすじの書き方で押さえるべき基本ポイント
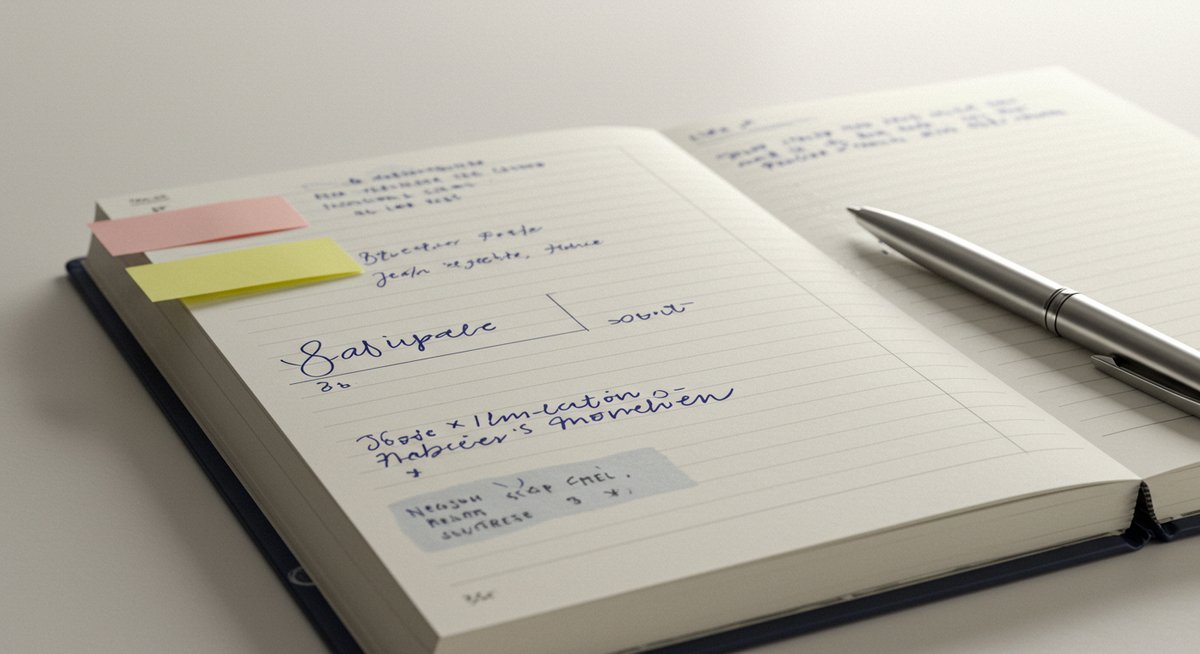
あらすじは作品を紹介したり、内容を伝えるための重要な文章です。まずは基本を押さえて、誰でも分かりやすいあらすじを書くコツを確認しましょう。
あらすじとは何か目的と意味を知る
あらすじとは、物語や作品の内容を短くまとめて説明する文章です。物語全体の流れや大事な部分を伝え、読む人に概要を理解してもらう役割があります。たとえば、本や漫画の裏表紙で見かける紹介文もあらすじの一例です。
また、あらすじは読む前の関心を引き出す役割も担います。物語全体の空気や魅力が伝わることで、興味を持ってもらいやすくなります。そのため、ただ内容を箇条書きするだけでなく、「どのような話なのか」「どんな雰囲気なのか」といった印象も含めて簡潔にまとめることがポイントです。
要約とあらすじの違いを理解する
要約とあらすじは一見似ていますが、目的や内容が少し異なります。要約は、物語の内容全体を端的にまとめて説明することが主な目的です。つまり、無駄な部分を省いて情報整理を重視します。
一方、あらすじは、読者が物語に興味を持つような工夫や、世界観の雰囲気を伝える表現も含めて書かれます。たとえば、要約では「主人公が困難を乗り越える」とまとめても、あらすじでは「主人公がどんな困難にどう立ち向かうのか」といった部分に触れ、読者の関心を引くことが求められます。
あらすじ作成で大切な情報整理のコツ
あらすじを書くときは、伝えたい内容を整理しながらまとめることが大切です。まず、物語の起承転結や大きな流れを簡単に書き出してみましょう。これにより、大事なポイントを見落としにくくなります。
また、登場人物や舞台、重要な出来事など、読者が理解しやすい順番で情報を並べることもポイントです。次の表のように、項目ごとに短く整理するのもおすすめです。
| 項目 | 整理内容の例 |
|---|---|
| 主人公 | 名前、特徴 |
| 舞台 | 時代、場所 |
| 主要な出来事 | 大きな流れ、転機 |
「漫画で何を伝えるべきか」がわかる本!
著名な先生方のお話が満載で充実の一冊。
あらすじを書く前の準備と構成の考え方
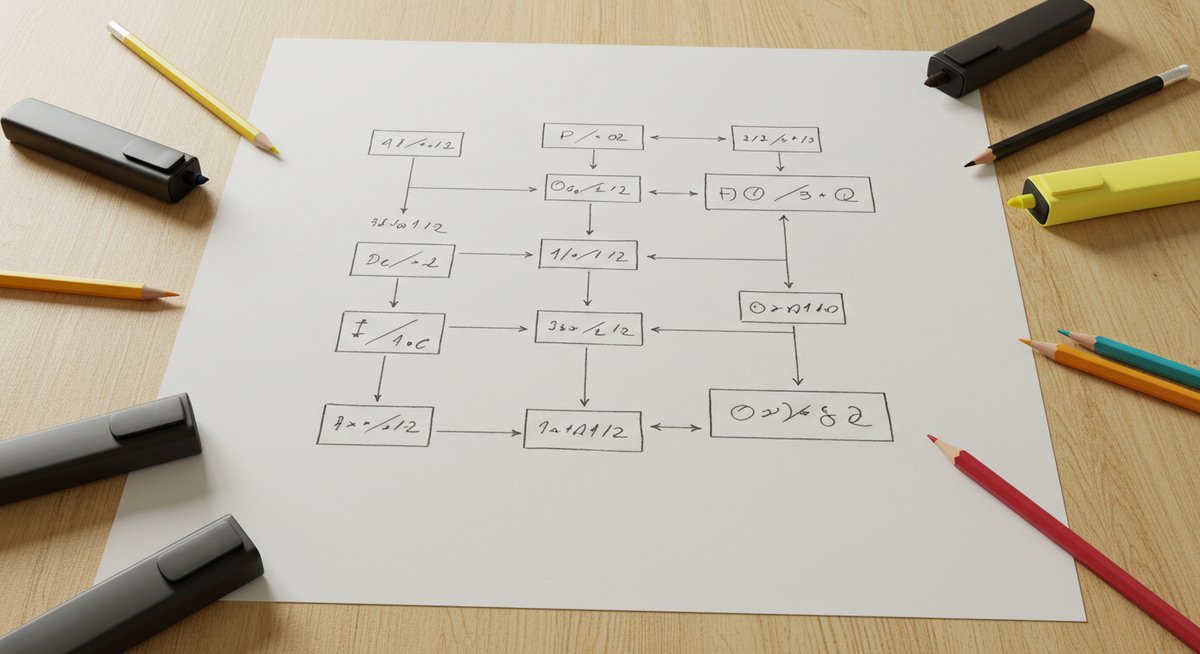
良いあらすじを書くためには、準備と構成の工夫が欠かせません。登場人物や物語の展開を整理し、伝わりやすい文章を作るコツを知りましょう。
物語の登場人物や舞台背景の整理方法
最初に登場人物や舞台背景をきちんと整理することで、あらすじが分かりやすくなります。主要なキャラクターを簡単なプロフィールとしてまとめておくと、文章に書くときに迷いにくくなります。
舞台背景も、「どの時代か」「どこで物語が進むか」といった情報を短くまとめておきましょう。たとえば、表にしておくと以下のようになります。
| 要素 | 内容例 |
|---|---|
| 主人公 | 田中ひろし、16歳の高校生 |
| 舞台 | 現代の東京、小さな商店街 |
| サブキャラ | 幼なじみ・友人・家族など |
このように準備することで、あらすじを書く際に必要な情報をすぐに参照できます。
重要な出来事や展開を抽出する手順
物語の中で特に大事な出来事や展開を把握することは、あらすじ作りに欠かせません。まずは物語をざっと振り返り、「物語が動いた場面」や「主人公が変化するきっかけ」をメモしましょう。
次に、その中でも読者が知っておくべきポイントだけを選びます。箇条書きにして、物語の流れが分かるよう整理すると、あらすじの骨組みが作りやすくなります。大事なのは、内容を絞り込みすぎず、かといって情報を詰め込みすぎないバランスです。
結末や転換点を分かりやすくまとめる方法
あらすじでは結末や転換点をぼかしつつも、物語の魅力や盛り上がりが伝わるよう工夫しましょう。たとえば、「主人公は大きな決断を迫られる」「物語は思わぬ方向に進む」といった表現を使い、詳しい結末までは書かずにまとめます。
また、結末を明かしすぎないことで、読者の興味を引くことができます。話の流れや転換点を簡潔に伝えつつ、続きが気になるような終わり方を意識すると、印象に残るあらすじになります。
読者を惹きつけるあらすじの工夫とテクニック

あらすじはただ内容をまとめるだけでなく、読者の興味を引くための工夫が欠かせません。表現や構成を工夫して、印象的なあらすじに仕上げましょう。
書き出しで興味を引く表現のバリエーション
あらすじの書き出しは、読者の関心を引く大切な部分です。たとえば、印象に残るセリフや「もしも~だったら」といった問いかけ、意外性のある出来事から始める方法があります。いくつか具体例を紹介します。
- 主人公の印象的な行動や言葉で始める
- 大きな事件や転機から描写する
- 読者への問いかけや疑問形で始める
このようなバリエーションを使い分けることで、最初から注目してもらいやすくなります。
5W1Hを活用した分かりやすい構成例
「誰が(Who)」「いつ(When)」「どこで(Where)」「何を(What)」「なぜ(Why)」「どうやって(How)」の5W1Hを意識すると、情報が整理されて分かりやすいあらすじになります。例えば、以下のような順番でまとめると効果的です。
- 誰が:主人公や主要なキャラクター
- どこで・いつ:物語の舞台や時代背景
- 何を・なぜ:主要な出来事や主人公の目的
- どうやって:物語の中で起きる展開やアクション
この流れを押さえておくことで、読み手にとって理解しやすい構成が作れます。
適切な長さや分量を意識するポイント
あらすじの長さは、伝えたい内容や読む人の状況によって変わりますが、長すぎても短すぎても伝わりにくくなります。一般的には150~300文字程度が目安とされることが多いです。
ポイントは、無駄な説明を省きつつ、物語の魅力が伝わる内容に絞ることです。長くなりそうな場合は、重要な部分を整理して簡潔にまとめましょう。逆に短くなりすぎる場合は、舞台や主人公の特徴も少し加えてみてください。
より良いあらすじを書くためのチェックリスト
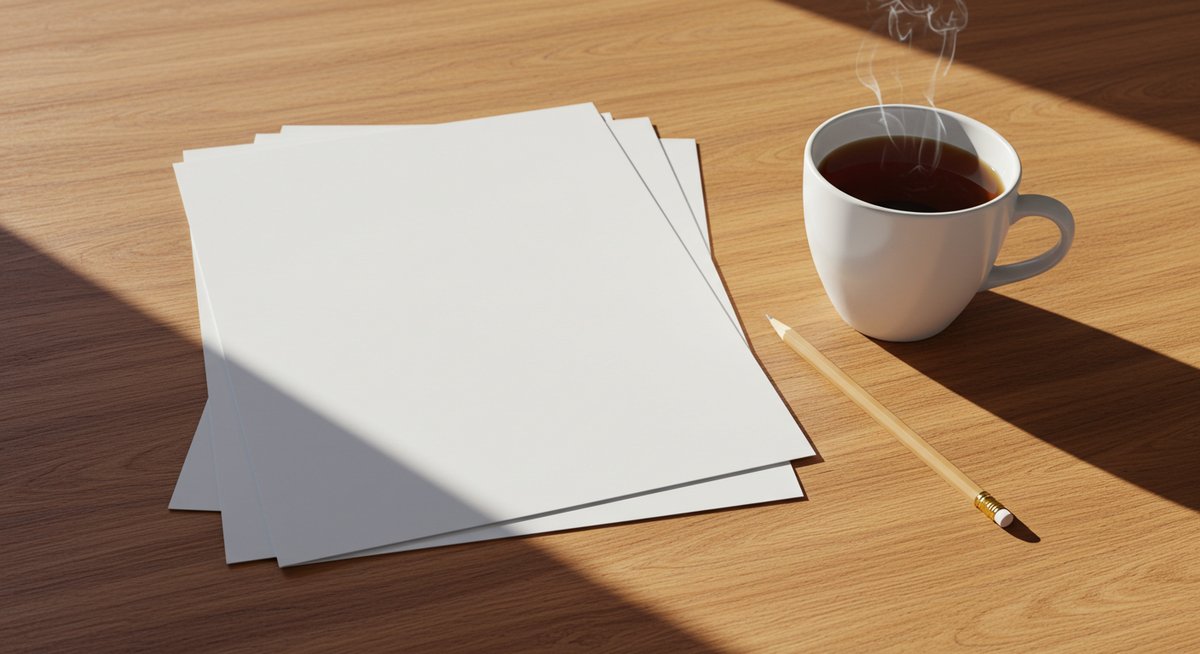
あらすじを書いた後は、内容の見直しや伝わりやすさの確認が大切です。チェックリストを参考に、より良いあらすじを目指しましょう。
客観性と一貫性を意識した見直し方
自分の感想や主観が入りすぎていないか、一貫した視点でまとめられているかをチェックしましょう。あらすじは、読む人が客観的に物語を理解できるよう心がけることが大切です。
また、内容に矛盾がないか、最初から最後まで同じ視点で書かれているかも確認しましょう。必要なら、友人や家族に読んでもらい、分かりやすさや説明不足になっていないか意見をもらうのもおすすめです。
ネタバレとのバランスを考える注意点
あらすじで結末や重要な秘密をすべて明かしてしまうと、読者の楽しみが減ってしまいます。どこまで内容を書くか迷った時は、「物語の流れは伝えるが、核心部分は伏せる」というバランスを意識しましょう。
たとえば、「主人公は最後に意外な決断をする」といった表現で結末をぼかしたり、大きな謎や問題が物語の中でどう扱われているかまでに留めておくのが安心です。
他人のあらすじ例を参考にする活用法
自分の表現に自信が持てない場合は、他の作品のあらすじを読んでみると参考になります。本や映画、漫画の公式サイトや帯に書かれているものをいくつか比べてみましょう。
気になった表現や分かりやすい構成、印象に残る書き方があればメモしておくとよいです。自分なりのアレンジを加えながら、「この表現いいな」と思えるものを積極的に取り入れることで、文章力は自然に伸びていきます。
まとめ:あらすじの書き方を身につけて伝わる文章を目指そう
あらすじの書き方には、情報整理や表現の工夫、ネタバレへの配慮など、さまざまなポイントがあります。基本を押さえつつ、読者目線で分かりやすい文章を心がけることが大切です。
あらすじは練習を重ねることで、少しずつ上達していきます。他の作品を参考にしたり、実際にいくつか書き比べてみたりしながら、自分だけの分かりやすいあらすじ表現をぜひ身につけてください。
世界70か国で愛されるコピック!
ペンにこだわると、イラストがどんどん上達します。