デッサン用鉛筆の基礎知識と選び方

デッサンに使う鉛筆には、一般的な鉛筆とは異なる特徴があります。自分に合った鉛筆を選ぶことで、描写の幅が広がり、作品の完成度も高まります。
デッサン用鉛筆と一般鉛筆の違い
デッサン用鉛筆と一般的な鉛筆には、芯の硬さや質、描き心地などに違いがあります。デッサン用鉛筆は、細かな濃淡や繊細な線を表現しやすいように作られており、鉛筆の芯自体も滑らかで均一な仕上がりです。
また、デッサン用は硬度のバリエーションが豊富で、HやBなどの記号で硬さが示されています。一般の鉛筆は主に文字を書く用途が中心で、HBやB程度の硬度が一般的ですが、デッサン用は非常に柔らかいものから硬いものまで揃っているため、描きたい表現に合わせて使い分けることができます。
鉛筆の硬度と表現の幅
鉛筆の硬度は、線の濃さや質感に影響します。一般的に、H系は硬くて薄い線を描くのに適しており、B系は柔らかくて濃い線が出せます。たとえば、輪郭や細部を描きたいときはH系を使い、影やボリュームを表現したいときはB系を使うのが一般的です。
下記は硬度と表現の違いをまとめた表です。
| 硬度 | 特徴 | 主な用途 |
|---|---|---|
| 2H~H | 硬め・薄い線 | 下描きや細部描写 |
| HB | 標準的な硬さ | 総合的に使える |
| B~6B | 柔らかい・濃い | 影や陰影表現 |
硬度を組み合わせて使うことで、質感や立体感を自在に演出できるので、いろいろ試してみるのがおすすめです。
初心者におすすめの鉛筆セット
初めてデッサンに挑戦する場合は、数種類の硬度がセットになったものを選ぶと便利です。代表的なのは、HB、2B、4Bなどがバランスよく入っているセットで、これだけでさまざまな表現が可能になります。
市販のデッサン用鉛筆セットには6本~12本入りなどがあります。迷ったときは、主要メーカーの初心者向けセットを選ぶと、品質も安定していて使いやすいです。セット内容をよく確認し、使い勝手のよい硬度が含まれているかチェックしてみてください。
「漫画で何を伝えるべきか」がわかる本!
著名な先生方のお話が満載で充実の一冊。
主要メーカー別デッサン用鉛筆の特徴

国内外には多くの鉛筆メーカーがあり、それぞれ微妙な描き味や仕上がりに違いがあります。お気に入りのメーカーを見つけるのもデッサンの楽しみのひとつです。
三菱鉛筆ハイユニとユニの違い
日本の老舗メーカーである三菱鉛筆の「ハイユニ」と「ユニ」は、どちらもデッサン用として人気がありますが、描き味や仕上がりに違いがあります。「ハイユニ」は芯がとても滑らかで、濃淡の表現がしやすいのが特長です。また、芯の折れにくさや摩耗のバランスも良好で、長時間のデッサンでも使いやすいです。
一方、「ユニ」はややしっかりとした描き心地で、線をコントロールしやすいのが特徴です。価格も「ハイユニ」より少し手頃なので、気軽に使いたい方や練習用としてもおすすめです。どちらも品質が高いので、好みや用途に合わせて選んでみてください。
ステッドラーとファーバーカステルの個性
ドイツのステッドラーとファーバーカステルは、世界中で支持されている鉛筆ブランドです。ステッドラーは、芯が折れにくく、シャープな線が描きやすいことが特徴です。特にハード系(H系)の描写で安定感があります。
ファーバーカステルは、やや柔らかめで滑らかな描き心地が魅力です。B系の濃淡が美しく出るため、陰影やグラデーションを表現したいときに重宝します。両者とも品質に定評があり、それぞれの個性を活かして使い分けると、作品の幅が広がります。
海外ブランドの注目アイテム
海外ブランドにも、個性豊かなデッサン用鉛筆がそろっています。たとえば、カランダッシュ(スイス)は鮮やかな黒や均一な線が描ける点で多くの画家に選ばれています。また、ダーウェント(イギリス)は、やや太めでしっかりとした芯が特徴で、幅広い表現に向いています。
海外ブランドの鉛筆は、パッケージデザインやカラーリングも魅力的です。国内メーカーにはない独特の描き味を体験できるので、気になる方は一度試してみるのもよいでしょう。
デッサン用鉛筆の使い方とメンテナンス
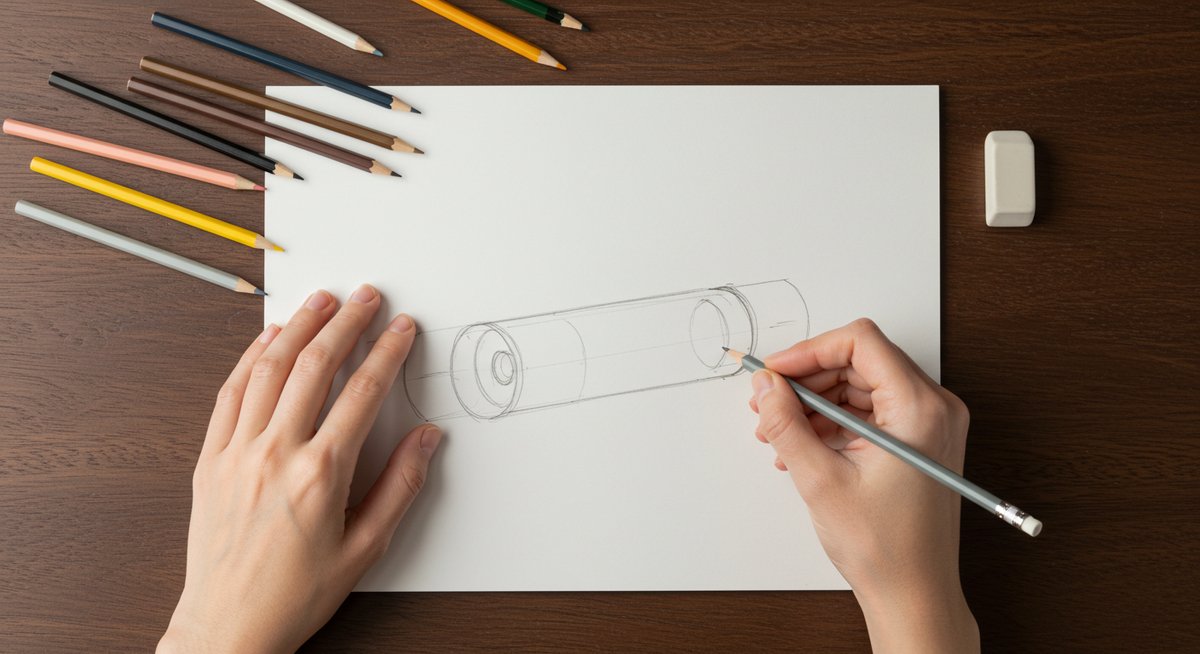
鉛筆は正しく使い、適切にメンテナンスすることで、より快適にデッサンを楽しむことができます。基本を押さえておくと表現の幅も広がります。
鉛筆の持ち方と線の描き分け
鉛筆の持ち方にはいくつかの方法があり、それぞれで描きやすい線やタッチが変わります。一般的な持ち方は、文字を書くときと同じ「筆記持ち」です。細い線や正確な描写に適しており、輪郭や細部を描くときに使います。
一方、鉛筆を寝かせて持つ「スケッチ持ち」では、広い面や柔らかな陰影を描くのに向いています。手首や腕を大きく動かして線を引くことで、自然なリズムや勢いのある表現ができます。場面に応じて持ち方を変えることで、線のニュアンスや質感をコントロールしやすくなります。
鉛筆の削り方とおすすめの道具
鉛筆の削り方は、描き心地や線の太さに大きく影響します。通常の鉛筆削り器でも削れますが、デッサン用にはナイフ(カッター)で芯を長めに出して削る方法が好まれます。芯を長く出すことで、広い面を使った塗りや繊細な線描がしやすくなります。
道具としては、以下のようなものがあると便利です。
- 小型のカッターナイフ
- 紙やすり(芯先の調整用)
- 卓上の鉛筆削り(手軽に使いたい場合)
芯が折れやすい場合は無理に削らず、少しずつ丁寧に削ると失敗しにくいです。
芯の素材ごとの扱いのポイント
デッサン用鉛筆の芯には、黒鉛が主に使われていますが、製品によって微妙に成分や硬さが異なります。硬い芯(H系)は、力を入れすぎると紙が傷みやすいので、やさしく描くことを意識しましょう。
柔らかい芯(B系)は、紙につきやすく、手や周りを汚しやすいので、こまめに手を拭いたり、紙をカバーするシートを使うと快適です。また、削ったあとの芯先はデリケートなので、落とさないよう注意し、使用後はケースや鉛筆キャップで保護すると長持ちします。
デッサンに役立つその他の画材と便利アイテム

鉛筆だけでなく、消しゴムや用紙などの周辺画材も、デッサンの仕上がりに大きく影響します。自分に合った道具をそろえておくと作業がスムーズです。
消しゴムや練り消しの選び方
消しゴムには、一般的なプラスチック消しゴムと、形を自由に変えられる練り消しの2種類があります。プラスチック消しゴムは、細部をしっかり消したいときや、はっきりとした修正をしたいときに便利です。
練り消しは、柔らかく伸ばせるため、微細な部分の修正や、やさしくトーンを調整したいときに向いています。広い部分を一度に消すよりも、色をうっすら取り除く用途で重宝されます。両方持っておくと用途によって使い分けができるのでおすすめです。
スケッチブックや用紙の種類
デッサンに使う用紙は、紙質や厚み、サイズによって描きやすさが大きく変わります。スケッチブックは一般的に中目(表面がややざらついているもの)が使いやすく、鉛筆のノリが良いため初心者にもおすすめです。
また、紙が薄すぎると消しゴムで破れやすく、厚すぎると持ち運びが大変になることもあります。用途や好みに合わせて、数種類のスケッチブックやバラ紙を試してみると、自分に合った紙質が見つかりやすくなります。
あると便利な補助画材
デッサン作業を快適に進めるためには、補助的な画材も役立ちます。たとえば、手を汚さないように敷く紙(当て紙)や、鉛筆の芯の調整に使う紙やすりなどが挙げられます。
他にも、仕上げの際には定規やコンパスが便利なこともあります。これらのアイテムをうまく使うことで、作業効率が上がり、より快適にデッサンに集中できるようになります。
まとめ:自分に合ったデッサン用鉛筆と画材を選んで表現力を高めよう
デッサンを楽しむためには、自分が使いやすい鉛筆や画材を選ぶことが大切です。いろいろと試しながら、自分だけの組み合わせを見つけてみてください。
鉛筆や用紙、消しゴムなど、それぞれの特徴を知って使い分けることで、表現の幅が広がります。基本的な使い方やメンテナンスも押さえて、より豊かなデッサンの時間を過ごしましょう。
世界70か国で愛されるコピック!
ペンにこだわると、イラストがどんどん上達します。











