漫画やイラスト制作で「理想の水色が作れない」「思った通りの雰囲気が出ない」と感じたことはありませんか。水色は空や海、衣服など多くの場面で使われる大切な色ですが、ほんの少しの違いで印象が大きく変わります。
色の配合や混ぜ方、画材選びのちょっとしたコツを知ることで、表現の幅が広がり、作品の完成度も上げられます。この記事では、水色作りの基本から応用まで、初心者でも分かりやすいよう丁寧に解説します。
水色の作り方と配合のコツを徹底解説

水色を美しく表現するためには、色の組み合わせや混ぜる比率にコツがあります。ここでは基本的な作り方から、アレンジ方法や印象を変えるポイントを紹介します。
青と白で作る基本の水色
水色を作る最もシンプルな方法は、青と白を混ぜることです。まず、青の絵の具をパレットに出し、少しずつ白を加えます。このとき、白を一気に混ぜすぎると、想像より明るくなりすぎることがあるので、少量ずつ調整することが大切です。
また、青と白の配合割合によって、水色の明るさや鮮やかさが大きく変わります。やや青が強いと爽やかで透明感のある水色になり、白が多いと優しいパステル調の水色になります。まずは小さな量で色を試しながら、理想の水色に近づけていきましょう。
エメラルドグリーンや黄色を加えたアレンジ方法
水色に個性や深みを加えたい場合、エメラルドグリーンや黄色など、他の色を少量加えてみる方法があります。たとえば、青と白にエメラルドグリーンを混ぜると、透明感のある爽やかな水色になります。黄色をほんのわずか加えることで、明るさと温かみがプラスされ、自然な空や水面の色を表現しやすくなります。
他にも、パレットで混ぜる色の順番や配合量を工夫することで、同じ「水色」でも様々なニュアンスが楽しめます。下記の表を参考に、簡単な配合例を試してみてください。
| 組み合わせ | 仕上がりの特徴 | 用途例 |
|---|---|---|
| 青+白 | 基本の水色 | 空、青い服 |
| 青+白+エメラルドG | 透明感、爽やかさ | 水、ガラス |
| 青+白+黄色 | 優しい、温かみ | 朝焼け、春の空 |
青の種類で水色の印象が変わる理由
水色を作る際に使う「青」の種類によって、出来上がる水色の雰囲気が大きく異なります。例えば、ウルトラマリンブルーは赤みがあり、柔らかく落ち着いた水色に。一方、シアンやセルリアンブルーは緑みを帯び、より鮮やかで爽やかな水色が作れます。
また、メーカーによって同じ名前でも色味に微妙な違いがあるので、いくつかの青を試して、自分の表現したいイメージに合ったものを選ぶことが大切です。イラストの雰囲気や季節感を出したいときは、青の種類にもこだわってみましょう。
水色の濃さや明るさの調整テクニック
思い通りの水色を作るには、濃さや明るさの調整がポイントです。水色が濃すぎたり暗く感じるときは、白を少しずつ足していきます。逆に、薄すぎると感じた場合は青を加えて調整します。特に水彩絵の具の場合は、水の量でも明るさや透明感が変わりますので、筆に含ませる水分量にも注意しましょう。
また、塗る紙や下地の色によっても見え方が違います。紙が黄みを帯びていると、水色がくすんで見えることがあります。最初は小さな面積で試し塗りをしてから、本番のイラストに使うと失敗が少なくなります。
「漫画で何を伝えるべきか」がわかる本!
著名な先生方のお話が満載で充実の一冊。
水色を作るときに知っておきたい混色の基本知識

水色を自分らしく作るためには、絵の具の色の混ぜ方や、その原理を知ることが役立ちます。ここでは混色の基本や、色の組み合わせについて解説します。
三原色と混色の原理を理解しよう
「三原色」は赤、青、黄色の3色で、これらを組み合わせることでさまざまな色が作れます。水色の場合、青をベースに、白で明るくするのが基本ですが、三原色の理解があると、他の色の調整もしやすくなります。
たとえば、ほんの少し黄色を加えることで、より自然な水色や緑寄りの色に調整できます。このように、色の混ぜ方とその効果の関係を知ることで、表現したい水色に近づけることができます。
補色や白黒の使い方で幅広い水色を表現
水色の幅を広げたいときは、補色や白・黒の使い方もポイントです。補色とは、色相環で正反対に位置する色のことで、水色ならオレンジ系が該当します。補色をほんのわずか混ぜると、色味が落ち着き、くすみ感が出ます。
また、白だけでなく少しだけ黒を加えると、グレイッシュな大人っぽい水色が生まれます。ただし、黒は加えすぎると濁りやすいため、少量ずつ様子を見ながら調整しましょう。
混色の順番が仕上がりに与える影響
混色をするとき、どの順番で絵の具を混ぜるかによって仕上がりの色が微妙に変わります。たとえば、青に白を加える場合と、白に青を加える場合では、発色やなじみ具合が異なる場合があります。特に白は量が多いので、少しずつ青を足す方法が失敗しにくいです。
また、複数色を混ぜるときは、主となる色を決めてから、副材料を加える、という流れで進めると、色が濁りにくくなります。一度に混ぜすぎず、段階を追って調整することをおすすめします。
絵の具の配合比率と色見本の活用法
理想の水色を安定して作るには、絵の具の配合比率を記録しておくと便利です。たとえば、「青2:白1」など、比率をメモしておけば、同じ色を再現しやすくなります。また、絵の具のメーカーや種類によって発色が異なるため、使用するたびに色見本を作ると安心です。
色見本は、以下のように配合と仕上がりを並べて比較できる表を作ると分かりやすいです。
| 配合例 | 仕上がり | メモ |
|---|---|---|
| 青1:白1 | 中間水色 | 明るさ標準 |
| 青1:白2 | 明るめ | 空や雲に最適 |
| 青2:白1 | 濃いめ | 海や影の表現 |
失敗しない水色作りのコツとよくある悩み
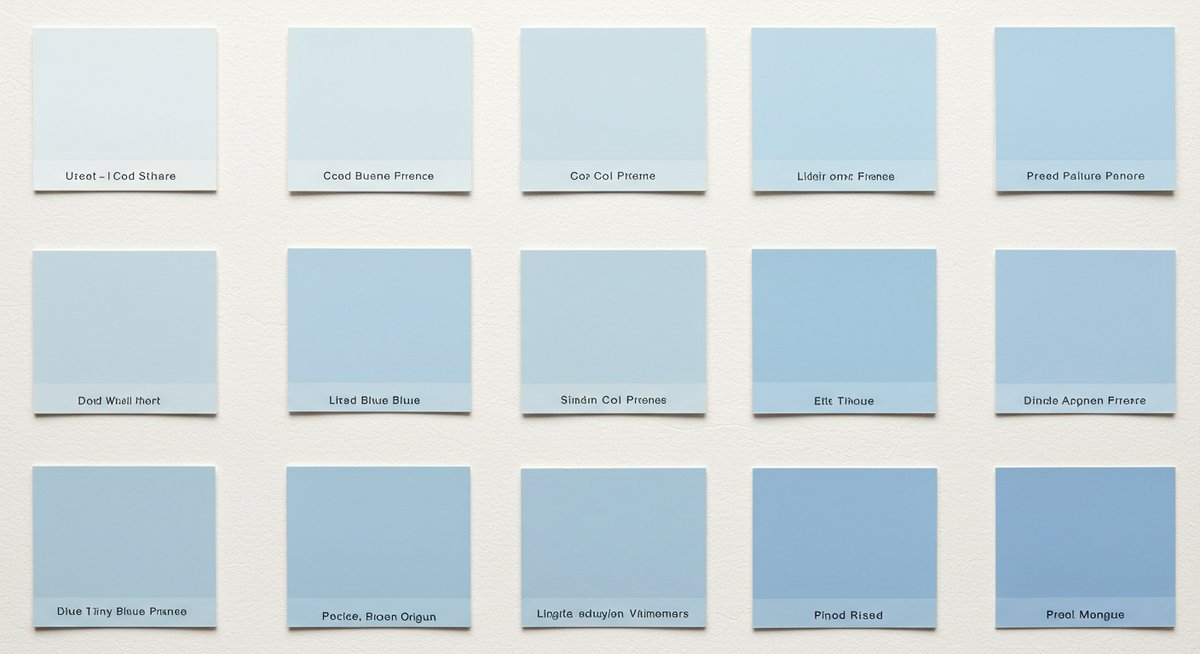
水色は一見シンプルですが、実際に絵に塗るとムラや濁りが気になることも多いです。ここでは、よくあるトラブルとその対処法をまとめています。
色ムラやにじみが出たときの対処法
水色を塗ったときに色ムラやにじみが出やすい場合、まず筆やパレットの水分量を見直すことが大切です。水彩の場合は特に、水の量が多すぎると紙ににじみやムラが発生しやすくなります。
にじみやムラが目立ったときは、乾いた筆やティッシュで軽く押さえて余分な水分を取り除くと、落ち着きやすくなります。塗る前に紙を濡らしすぎないこと、重ね塗りをする場合は十分に乾かしてから作業することもポイントです。
水色が濁る原因と透明感を出す方法
水色がくすんで見える、思ったような透明感が出ない場合は、混ぜる色が多すぎたり、絵の具が重なりすぎていることが考えられます。特に青以外の色や黒系を多用すると、濁りやすくなります。
透明感を出したい場合は、青と白だけでシンプルに仕上げたり、絵の具を薄く水でのばして塗るとよいです。また、明るい紙や下地を使うことで、発色がより美しくなります。なるべく少ない色数で仕上げることも、透明感アップのポイントです。
希望の水色にならないときのリカバリー術
混色で意図しない色味になった場合は、まず少しずつ白を足して様子を見ましょう。明るさが戻ることで、イメージに近づくことがあります。また、青や他の色を一度にたくさん加えると、さらに色がずれてしまうので注意が必要です。
どうしても元に戻らない場合は、最初から新しく少量ずつ混ぜ直すのが失敗しにくいです。事前に試し塗りや色見本を作っておくことで、リカバリーがしやすくなります。
紙や絵の具による発色の違いを知る
同じ水色を作っても、使う紙や絵の具のメーカーによって発色が変わります。たとえば、つるつるした紙よりも、凹凸のある紙は色が沈んで見えることが多いです。また、メーカーごとに青や白の色味が異なるので、同じ配合でも少し違った仕上がりになることも。
初めて使う画材の場合は、かならず色見本を紙に塗って確認しておきましょう。普段よく使う組み合わせを表にしておくと、次から迷わずに水色を選ぶことができます。
シーン別水色の作り分けと応用テクニック

水色は空や海、ファンタジー背景など多くの場面で使われます。ここでは描きたいシーンごとに適した水色の選び方や表現方法を紹介します。
空や海など自然を描くときの水色の選び方
空や海を描くときは、時間帯や天候によって水色の印象が大きく変わります。昼間の空なら、やや白を多めにした明るい水色が適しています。逆に、夕方や雨の日の空は、グレーや青紫を少し加えて落ち着いたトーンにすると、リアルな雰囲気が出せます。
海の場合は、浅瀬は明るい水色、深い部分は青みや緑みを強くすると奥行きが表現できます。場面によって水色の配合を調整し、自然なグラデーションを意識して塗ると、作品のリアリティがアップします。
ターコイズブルーや個性的な水色を作る方法
一般的な水色以外にも、ターコイズブルーのような個性的な色味を作りたいときは、青にエメラルドグリーンやごく少量の黄色を加えるのがおすすめです。透明感を残しつつ、鮮やかで印象的な水色が作れます。
また、個性的な水色を作るコツは、少しだけ赤や紫を加えてニュアンスを調整することです。使う色の種類や配合を変えることで、自分だけのオリジナルな水色が作れるので、いろいろ試してみてください。
水彩とアクリルでの水色表現の違い
水彩絵の具は水で薄めることで透明感が出しやすく、淡い水色やグラデーションを自然に描くのが得意です。一方、アクリル絵の具は発色がはっきりしており、隠ぺい力が高いので、パキッとした水色や厚塗り表現に向いています。
それぞれの特徴を活かし、場面や好みに応じて使い分けてみましょう。たとえば、空のグラデーションには水彩、ポップな背景やデジタル風のイラストにはアクリルが合うことが多いです。
デジタルイラストで理想の水色を作るコツ
デジタルイラストでは、カラーピッカーを使って青系と白系の中間色を選ぶことで簡単に水色が作れます。最初は基本の水色をベースにし、レイヤーの不透明度やブレンドモードを工夫することで、より自然な透明感や立体感を出すことも可能です。
また、色相・彩度・明度ツールを使えば、後から調整もしやすくなります。複数の水色を重ねてグラデーションにしたり、個性的な水色をパレットに登録しておくと、時短にもつながります。
画材選びと道具の工夫で水色表現を広げる
理想の水色を表現するには、絵の具や筆、パレット選びも重要です。ここでは道具選びのポイントや便利なアイテムを紹介します。
水色をきれいに出すおすすめの絵の具ブランド
水色の発色や混色のしやすさは、使う絵の具ブランドによって違いが出ます。発色が鮮やかで混ぜやすいブランドを選ぶことで、理想の水色を作りやすくなります。
たとえば、以下のようなブランドは水色表現が得意です。
| ブランド名 | 特徴 | 向いている表現 |
|---|---|---|
| ホルベイン | 発色・混色がしやすい | 水彩の淡い水色、グラデ |
| ウィンザー&ニュートン | 透明感が高い | 明るい水色、重ね塗り |
| ターナー | 発色が鮮やか | ポップな水色、厚塗り |
パレットや筆の選び方とメンテナンス
パレットは色をきれいに混ぜやすいものを選ぶと、水色の濁りを防げます。白い陶器のパレットや、広めの作業スペースがあるものがおすすめです。筆は、細い線が描けるラウンド型や、広い面を塗れるフラット型を用途で使い分けると便利です。
また、色移りや混色の失敗を防ぐためにも、使用後はしっかり洗ってメンテナンスすることが大切です。筆の根元までやさしく洗い、よく乾かしてから保管しましょう。
初心者でも扱いやすい画材の特徴
初心者には、発色が安定していて混色しやすい絵の具や、持ちやすい筆が扱いやすいです。水彩絵の具ならチューブタイプが混ぜやすく、アクリルなら速乾性が高すぎないものが安心です。
また、最初はセットになったパレットや、色数が多めのスターターセットを使うと、いろいろな水色を簡単に試せます。迷ったときは、口コミやレビューも参考にして選ぶとよいでしょう。
混色を楽しむための便利グッズ紹介
混色を快適にするアイテムには、洗いやすい大きめパレットや、混色用の専用スプーン、スポイトなどがあります。スポイトを使うと、正確に水や絵の具を加えられるので、色の微調整がしやすくなります。
また、使い捨てパレットペーパーや、色見本カードもあると便利です。いくつかの便利グッズを活用して、混色の失敗や手間を減らし、制作を楽しみましょう。
まとめ:水色の作り方をマスターして表現の幅を広げよう
水色は、少しの配合や混ぜ方の違いでさまざまな表情を見せてくれる色です。基本の作り方や混色のコツ、道具の選び方を知ることで、より理想に近い表現が可能になります。
自分だけの水色を見つけて、イラストや漫画の表現をさらに豊かにしていきましょう。日々の制作でも、少しずつ工夫や実験を重ねることが、上達への近道です。
世界70か国で愛されるコピック!
ペンにこだわると、イラストがどんどん上達します。











