日本画に描かれる雲は、単なる空の一部ではなく、物語の背景や雰囲気を作り出す大切なモチーフです。しかし「雲の描き方が分からない」「どんな画材を選べばよいのか迷う」といった悩みを持つ方も少なくありません。
この記事では、日本画における雲の歴史や意味、具体的な画材の選び方、描き方のコツまで、丁寧に解説します。これから日本画に挑戦したい方や、作品に雲を取り入れたい方の不安を少しでも軽くできる内容を目指しました。
日本画に描かれる雲の歴史と意味を知ろう

日本画において雲は、単なる自然現象以上の意味を持ち、長い歴史の中で多彩な表現が生まれました。ここでは雲がもつ象徴や、その変遷について解説します。
日本画における雲の象徴的な意味
日本画における雲は、現実の天気を表すだけでなく、神秘的な空間や時間の区切り、また物事の境界を示す重要なモチーフです。特に神話や伝説の場面では、雲は神聖さや非日常を象徴し、人や物の存在を際立たせる役割を担います。
さらに、雲は「見えないもの」「移ろいゆくもの」として、人生のはかなさや世の中の変化を表現する手段にもなっています。そのため、雲の形や色、配置には画家それぞれの思いが込められていることが多いです。
浮世絵や屏風絵で描かれる雲の役割
浮世絵や屏風絵では、雲は場面の区切りや物語の転換点を示すために使われています。たとえば、舞台を分けたり、神や貴人の登場シーンで雲を配置することで、観る人に特別な印象を与えます。
また、雲には空間の奥行きや広がりを持たせる効果もあります。屏風絵のような大きな作品では、雲の配置や重なり方によって、登場人物や風景の位置関係がより明確になり、物語の流れが自然に伝わります。
雲のデザインが時代ごとに変化した理由
雲のデザインは時代ごとに大きく変化してきました。平安時代には、柔らかく流れるような雲が好まれましたが、戦国時代や江戸時代には、装飾的で力強い雲が描かれるようになります。これは時代背景や美意識、技術の発展と深く関係しています。
たとえば、金箔や銀箔が使われ始めると、雲はより華やかに、抽象的な装飾要素として描かれる場面も増えました。社会の変化や画材の進化が、雲の表現にも大きな影響を与えてきたのです。
有名な日本画家が描いた雲の特徴
有名な日本画家が描いた雲には、それぞれ独自の特徴があります。たとえば、尾形光琳の雲は金箔を用いた装飾的な美しさが引き立っています。一方で、狩野派の作品では、力強い輪郭線と重厚感のある表現が特徴的です。
また、近代以降の日本画家は、伝統的な雲の表現を基礎にしつつ、自然な陰影や透明感を活かした描き方を取り入れています。画家ごとの雲の描き方を比較すると、その時代の美意識や個人の感性の違いがよく分かります。
「漫画で何を伝えるべきか」がわかる本!
著名な先生方のお話が満載で充実の一冊。
日本画に使われる主な画材とその選び方

日本画で雲を描くには、絵の具や筆、和紙など、独特の画材が使われます。適切な画材選びが表現の幅を広げるポイントです。
日本画特有の絵の具とその発色
日本画に使われる絵の具は、「岩絵具」や「水干絵具」と呼ばれるものが主流です。岩絵具は鉱石を細かく砕いて作られ、鮮やかで重厚な色合いが特徴です。一方、水干絵具は、顔料を膠(にかわ)で固めたもので、発色がやや柔らかく繊細な表現に向いています。
雲を描く際は、白や淡い青、グレーなどを選ぶことが多いですが、岩絵具と水干絵具では同じ色でも雰囲気が大きく異なります。特に雲のグラデーションやぼかしを表現したい場合は、水分や膠の量を調整しながら塗ることが大切です。初心者の場合は、まずは水干絵具から試してみるとよいでしょう。
筆や刷毛の種類と描き分けのコツ
日本画で使う筆や刷毛には多くの種類がありますが、雲を描く際には柔らかい羊毛筆や、ぼかしに使いやすい刷毛が役立ちます。細い線が必要な場合は、面相筆と呼ばれる細筆を使うと繊細な表現ができます。
筆の持ち方や動かし方も重要なポイントです。柔らかい筆で軽くなでるように描くと、雲がふんわりとした印象になります。逆に、硬めの筆や平筆を使って筆跡を残すことで、力強さや装飾性を持たせることも可能です。いくつかの筆を使い分けてみることで、雲の表情をより豊かにすることができます。
雲を描く時に使われる和紙の特徴
日本画で用いる和紙は、にじみやぼかしなど独自の表現ができるため、雲を描くのに適しています。特に「雲肌麻紙」や「鳥の子紙」は、絵の具の吸い込み具合が程よく、柔らかい雲の質感を出しやすいです。
和紙の選び方によって仕上がりは大きく変わります。吸水性の高い和紙を選ぶと、絵の具がじんわりと広がり自然なグラデーションが作れますが、にじみすぎる場合は下地に膠を薄く引くことでコントロールできます。紙の厚さや質に注目し、自分の描きたい雲に合った和紙を選ぶことがポイントです。
金箔や銀箔を使った雲表現のテクニック
金箔や銀箔は、日本画ならではの雲表現を支える素材です。貼り付けた箔の上に薄く絵の具を重ねることで、きらめきと奥行きを持った雲が生まれます。これにより、画面全体の華やかさや格調が高まる効果があります。
箔を使う際は、接着剤となる膠を均一に塗り、乾き具合を見てから箔を貼ることが大切です。絵の具で輪郭や陰影を加えると、より立体的で印象的な雲を表現できます。箔の扱いには慣れが必要ですが、少しずつ練習するとオリジナルの雲表現が楽しめるようになります。
日本画の雲を描くための基本技法
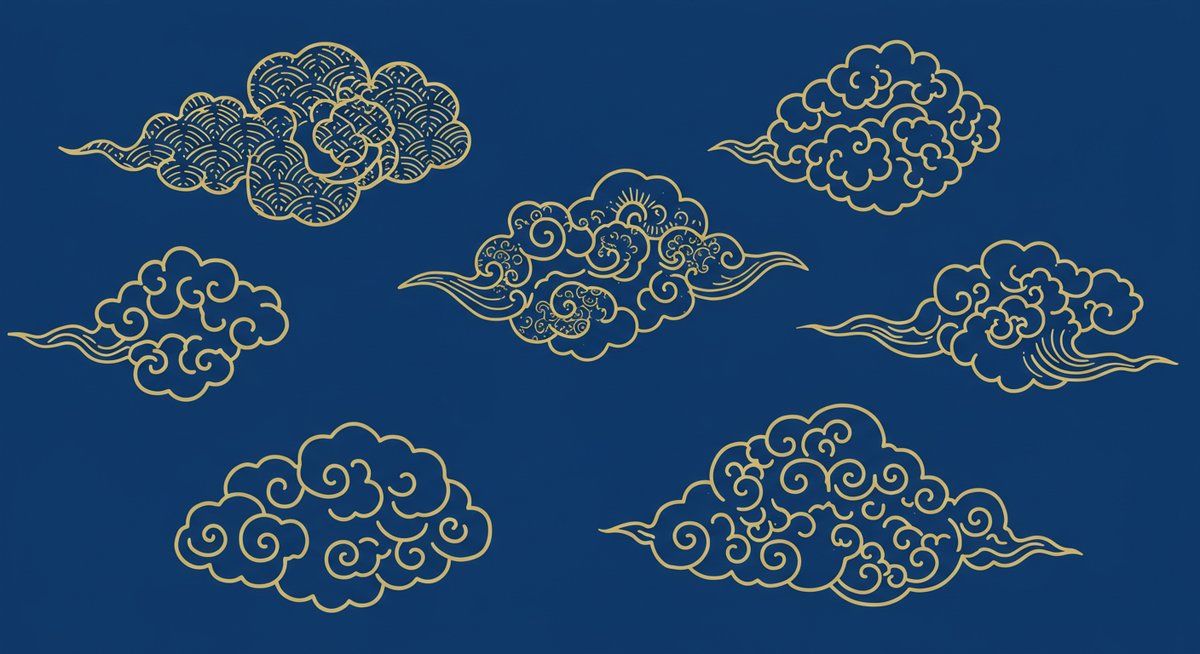
雲の表現には、日本画独自の技法が数多くあります。基本的な描き方や表現方法を知ることで、作品の完成度が大きく高まります。
すやり霞や金雲の描き方
「すやり霞」は、柔らかなグラデーションで雲を表現する技法です。まず淡い色を大きめの刷毛で塗り、その上から少し濃い色を重ね、乾かないうちに水を含んだ筆で境界をぼかします。こうすることで、滑らかな霞や雲の層が生まれます。
一方「金雲」は、金箔や金泥を使って描かれます。箔を貼った後、輪郭を筆で整えたり、部分的に重ねたりすることで、豪華な雲の表現が可能です。どちらも練習することで、伝統的な日本画らしい雲の雰囲気を身につけることができるでしょう。
ぼかしやにじみを活かした雲の表現法
雲の柔らかさや自然な動きを表現するには、ぼかしやにじみの技法が効果的です。最初に薄く絵の具を塗り、乾かないうちに水を含ませた筆で輪郭をぼかすと、ふんわりとした雲になります。
段階的に色を重ねていくことで、奥行きや立体感も生まれます。にじみの加減は和紙の種類や水分量によって変わるため、事前に試し描きをしながらコントロール方法を身につけるのがおすすめです。失敗しても重ね塗りで修正できるので、気軽に色々なぼかし方を試してみると良いでしょう。
レイヤー重ねで立体感を出すコツ
雲に立体感を持たせるためには、色や濃淡を変えながら何層にも重ねて描くのがポイントです。まず淡い色で全体の雲の形を描き、乾いた後に少しずつ濃い色を上から塗り重ねます。
この際、筆を変えて硬さや太さを工夫すると、質感の違いや奥行きがより表現しやすくなります。重なった部分にグラデーションをつけたり、部分的に色を抜いたりして微調整すると、よりリアルで表情豊かな雲に仕上がります。
初心者にもおすすめの練習方法
初心者が雲を描く練習をする際は、まず簡単な形から始めましょう。鉛筆で雲の輪郭を描き、水干絵具で淡く塗ってみるのが基本です。その上で、ぼかしやグラデーションの練習を繰り返すことで、自然な雲の表現が身につきます。
また、いろいろな筆や和紙を使って、同じ雲の形を描き比べてみるのも効果的です。失敗を恐れず、色々な技法を試してみることで、少しずつ自分らしい雲の描き方を見つけられます。教材として図案集や見本を使うのもおすすめです。
参考になる日本画の雲作品と図案集

日本画の雲表現を学ぶには、過去の名作や図案集を参考にすることがとても役立ちます。ここでは、雲の描き方や構図のアイデアが得られる資料を紹介します。
浮世絵の名作に見る雲の使い方
浮世絵の名作には、雲を巧みに使った作品が多く見られます。たとえば葛飾北斎や歌川広重の風景画では、雲が画面のアクセントや、物語の流れを示す要素として描かれています。
雲を配置する位置や形、大きさのバランスを見ることで、空間の広がりや奥行きの作り方が学べます。浮世絵は構図がシンプルでわかりやすいため、初心者にも参考にしやすい作品がそろっています。
明治時代の図案集「雲霞集」の魅力
「雲霞集」は、明治時代に作られた雲や霞の図案を集めた資料集です。この図案集にはさまざまな雲の形やパターンが掲載されており、伝統的なデザインから装飾的なものまで幅広く学べます。
雲の輪郭やグラデーションの描き方、金雲・銀雲のバリエーションなど、実際の作品づくりにもすぐに応用できるヒントが詰まっています。モチーフ選びやアレンジの際に活用してみると良いでしょう。
現代作家による雲モチーフの日本画
現代の日本画家も、雲をテーマにした新しい表現に挑戦しています。伝統的な技法を活かしつつ、色彩や形に独自のアレンジを加えている作品が増えています。
たとえば現代作家の作品では、抽象的な雲や、カラフルな色使いで個性を出しているものもあります。現代の作品を参考にすれば、今の時代らしい雲の表現や、自分だけのアレンジを考えるヒントになるでしょう。
無料でダウンロードできる雲の図案資料
最近では、インターネット上で無料ダウンロードできる雲モチーフの図案資料も充実しています。こうした資料を活用すると、気軽に多様な雲のデザインを研究したり、模写の練習に使うことができます。
【無料図案資料の主な特徴】
・伝統的な雲、現代風アレンジなど種類が豊富
・印刷して直接書き込みができる
・レイヤー練習や構図作成に応用しやすい
初めて雲を描く方や、さまざまなデザインパターンを探している方におすすめです。
雲をテーマにした日本画作品の鑑賞ポイント
日本画の雲を鑑賞する際は、色や構図、細部の表現に注目することで、作家の意図や物語をより深く感じ取ることができます。
色使いや構図から読み取る雲の表現意図
雲の色使いには、それぞれ意味や意図があります。たとえば淡い色調を選ぶことで静けさや幻想的な雰囲気を表現したり、濃い色や金箔を使うことで力強さや華やかさを演出しています。
また、雲の配置や形によって、画面の奥行きや視線の流れが決まります。構図が工夫されている作品ほど、雲の存在感が際立ち、物語性や場面の空気感が伝わってきます。
雲が演出する物語性や空間の広がり
雲は、絵の中で場面転換や時間の経過、神秘的な空間を表すために使われます。雲をうまく活用することで、画面に奥深さや広がりが生まれます。
たとえば、雲で人物や風景の一部を隠すことで、見えない部分への想像力をかき立てたり、空間や時間の移り変わりを表現できるのも、日本画の雲ならではの面白さです。
他モチーフと組み合わせた雲のバリエーション
日本画では、雲と他のモチーフを組み合わせて多彩な表現が行われています。たとえば、山や川、花鳥と雲を組み合わせることで、自然の移ろいや季節感が強調されます。
【雲と組み合わせる主なモチーフ】
・山 …壮大さや奥行きを演出
・花鳥 …優雅さや季節感を強調
・神仏 …神聖さや物語性を強める
雲のデザインや配置を工夫することで、自分だけのオリジナルな日本画表現が広がります。
鑑賞時に注目したい細部の工夫
雲の細部表現には、作家のこだわりや技術が反映されています。たとえば、雲の縁どりに金泥や銀泥を使ってきらめきを加えたり、微妙な色の重なりで立体感を作っている場合があります。
また、雲の中に繊細な線や模様を描きこむことで、より印象的な質感が生まれます。こうした細かな部分にも目を向けることで、日本画の奥深さや作家の個性をより楽しめるようになります。
まとめ:日本画の雲は画材と技法で無限の表現が広がる
日本画における雲の表現は、歴史や画家ごとの個性が反映された奥深い世界です。伝統的なモチーフでありながら、使う画材や技法次第で多彩な表現が可能になります。
初めて雲を描く方も、基本の画材選びや描き方を知ることで、自分らしい雲を自由に表現できます。過去の名作や図案資料を活用し、いろいろな描き方に挑戦してみてください。雲を描くことで、日本画の新しい魅力や楽しさに出会えることを願っています。
世界70か国で愛されるコピック!
ペンにこだわると、イラストがどんどん上達します。











